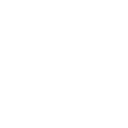2025 FALL WINTER COLLECTION

とりわけ2023AWコレクション以降に積み重ねてきた、エレガンスの獲得への挑戦としてデザイナーの胸裏に佇む女性の姿を通した超現実的な表現は、現代の東京における現実的な身体の不在を引き起こしうる諸刃の刃でもあった。
マジカルな概念であるエレガンスを日常生活や社会と接続するためには、現実への眼差しを立脚点とするのではなく、着地点を現実の世界に置く必要があった。
「KEISUKEYOSHIDAにとって10年の節目を迎えたことが、ブランドの道程と今一度対峙しデザインを反芻する最適な契機となりました」と吉田圭佑は語る。
過去のコレクションで誕生したエクストリームな造形のアイテムを社会性を帯びた身体へと近づけていくなかで2025AWコレクションは胎動したと言う。
緊張と厳かさのメタファーとして窮屈でドレッシーな表情を与えられたトレンチコートは、軽やかでデイリーユースな素材の再選択で普遍的なトレンチコートの在り様へと帰結。
猫背を象ったテーラードジャケットやチェスターコートも、抑制した緩やかなシェイピングと素材感の変化によってブランドの精神を内包しながらもウェアラブルなシルエットに更新された。
思春期の鋭敏な自意識が投影されたリボンシャツは、ボディの締め付けによって成熟した気品を纏った表情へと変化した。
オーディナリーな形状のウェアにもデザイナーのビジョンやエッセンスは息づく。
ナイロンの光沢感をシルクサテンの艶に置き換えて構成されたMA-1。
ウール素材の端正なフーデッドコートはナイロン素材のベンチウォーマーとリバーシブルで、カジュアルな表とモダンな裏を併せ持つ。
吉田が日頃使用するベッドマットレス柄のキルティングジャケットや実家の絨毯柄を用いたコートには、閉ざされた扉の内に存在する孤独な日々に散らばる品性の香りを発見した喜びが誇張なくデザインへと転化されている。
吉田は、スリップが脱げかかったようにぶら下がって崩れたデザインのマキシスカートに、無防備な所作の奥に見出したイブニングの気品を込めた。
銀紙に吐き捨てられたチューイングガムを模ったイヤリングは、反復する日常に埋もれる物質や仕草に注ぐ視線が本コレクションの根底に流れていることをまざまざと喚起する。
「閉ざされた部屋で孤独を抱えながら、自身を社会に浸透させようと試みることはとても苦しいことです。ただ、他者に置き換えて俯瞰すると、その在り方もそこに漂う浮遊感も美しいものとして映り、どうしようもなく惹かれてしまう。思えば、自らも孤独に救われているのかもしれないという矛盾が存在しているのです」
――心象の箱庭に沈む私的な美意識や寂寞の念をデイリーウェアへと昇華する作業は、自身と社会との距離を測り、その狭間に浮上する生き辛さや息苦しさを捉えることに似ている。
時を経てもなお、ナードで脆弱で、どうしようもないものに美を見出すデザイナーの根幹は揺らいでいない。
無数の孤独な個人の集合体こそ社会であり、そこには無数の装いが等しく存在する。
プレゼンテーション会場となったロサ会館も、戦後間もなく開業し、市井の人々がそれぞれに抱える孤独を埋め、やり過ごし、癒しを得る場であった。
青春時代を池袋で過ごした吉田にとってその姿はまさしく社会そのものであり、彼もまたその空間によって救われてきた無数の人間のうちの1人だった。
「しかし」と吉田は言い添える。
「自分の過去をありありと語るのは、もうこれで十分です」。